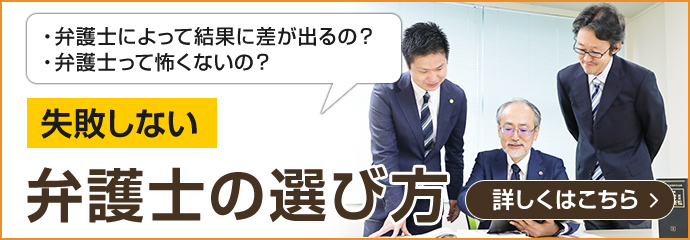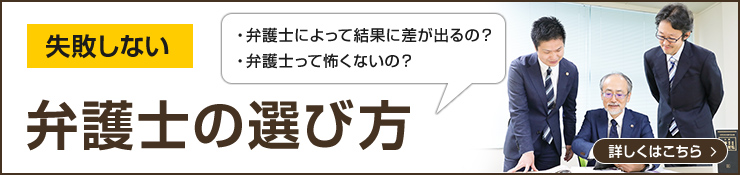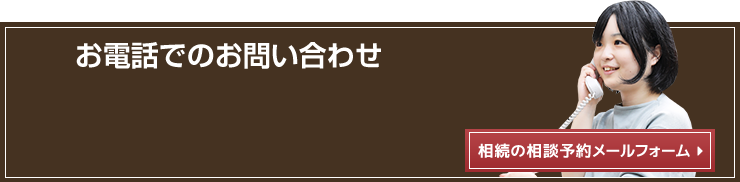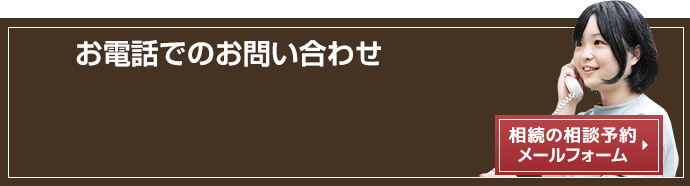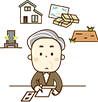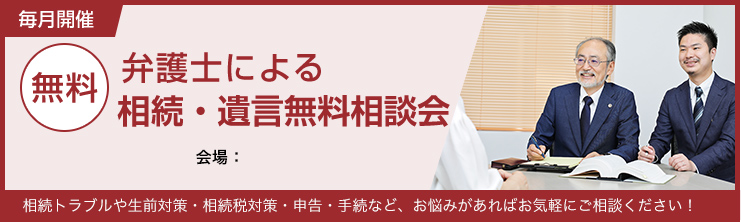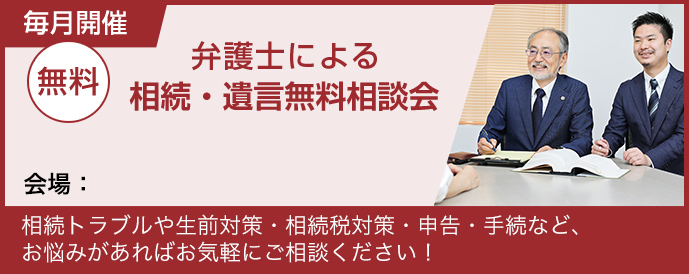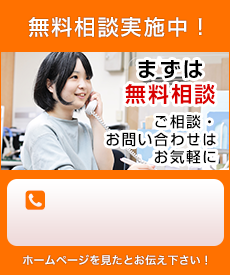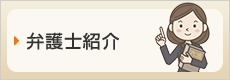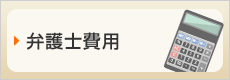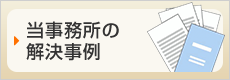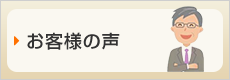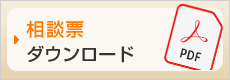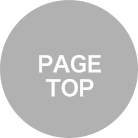相続Q&A
当事務所の解決事例を検索する
-
遺産分割は誰に頼むべき? 弁護士が解説
-
遺産分割は、相続人同士の話し合いだけで円満に進められる場合もありますが、現実にはトラブルに発展することが少なくありません。特に、財産の種類や分け方によっては、法的な知識が求められるため、適切な専門家に依頼することが重要で […]
-
遺産の評価に関して意見が異なります。どうやって解決すればよいでしょうか?
-
遺産の評価は、たとえば不動産の評価額について、相続人間で意見が分かれることがよくあります。この場合、専門の評価機関や不動産鑑定士など、第三者に正式な評価を依頼することが解決の一助となります。公平な評価をもとに、冷静に話し […]
-
相続人の一人が遺産分割協議に参加したがりません。どうすればいいですか?
-
相続人全員が協議に参加しなければ、法的に有効な遺産分割はできません。このような場合、弁護士を介してその相続人に参加を促すか、最終的には家庭裁判所での調停手続きを検討する必要があります。当事者間で無理に話し合いをするにも限 […]
-
相続の話し合いに感情的になりやすい相続人がいます。どう対処すべきでしょうか?
-
感情的になりやすい相続人がいる場合、無理にその場で結論を出そうとするのではなく、時間をかけて冷静に話し合いを進めることが大切です。また、専門家を交えて中立的な立場からアドバイスを受けることで、感情的な対立を緩和させること […]
-
親が生前に特定の相続人に多額の援助をしていました。この場合、遺産分割はどうなりますか?
-
親が生前に特定の相続人に対して援助を行っていた場合、それを「特別受益」とみなして遺産分割に反映させることがあります。この場合、他の相続人とのバランスを考慮し、その援助額を遺産に組み込んで分配が行われることが一般的です。 […]
-
遺言書がない場合、どのように相続が進むのでしょうか?
-
遺言書がない場合、相続は家族間での話し合いによって進められます。話し合いが円満に進めばよいのですが、もし、相続人の合意が得られない場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停を利用して解決することとなります。 ▼その他のQ& […]
-
相続手続きが複雑で困っています。どこに相談すればよいですか?
-
相続手続きが複雑な場合、まずは相続に詳しい弁護士や税理士に相談することをお勧めします。法的な手続きをスムーズに進めるためのサポートを提供してくれるだけでなく、相続税の問題にも対応してくれるので、安心して相談できます。 ▼ […]
-
相続人間で公平な分配が難しい場合、どのように対処すればよいですか?
-
公平な分配が難しい場合、感情的な判断に流されないように、財産の評価や分割に関して専門家のアドバイスを受けるのが賢明です。法的な基準に従った分配方法を提案し、全員が納得できる形で合意を形成することが重要です。 ▼その他のQ […]
-
財産の開示を求められたとき、どの程度まで情報を提供するべきですか?
-
財産の開示は相続の話し合いにおいて重要な要素です。すべての相続人が正確な情報を共有することで、相互の信頼を確保し、トラブルを防ぐことができます。必要な情報は、透明性を保ち、他の相続人に疑念を抱かせない範囲で提供しましょう […]
-
相続人同士での話し合いが行き詰まった場合、どのような対処をすればよいですか?
-
相続人同士で話し合いが行き詰まった場合、無理に話を進めるのは逆効果です。弁護士や第三者の専門家を早い段階で交え、法律に基づいた冷静な意見を取り入れることで、感情的な対立を避けることが可能です。 ▼その他のQ&Aは […]