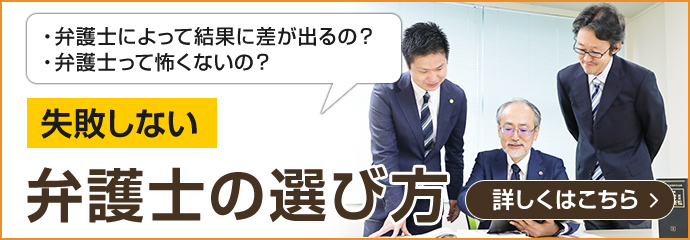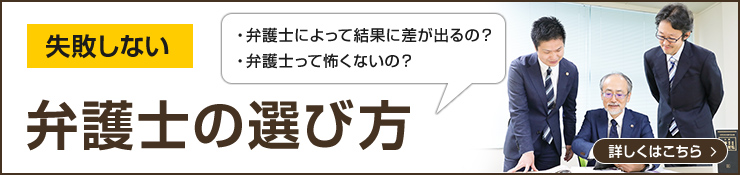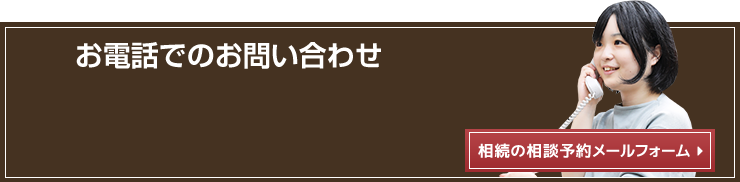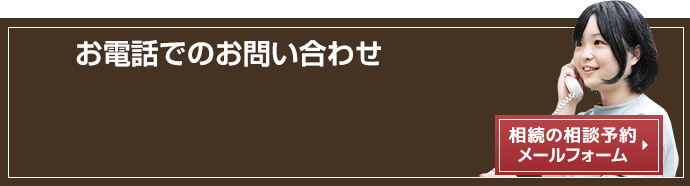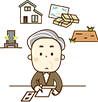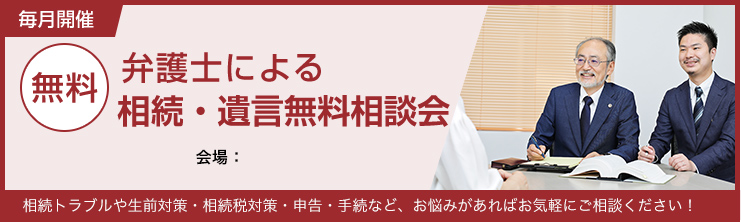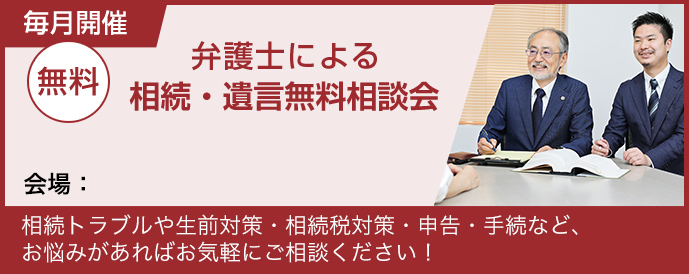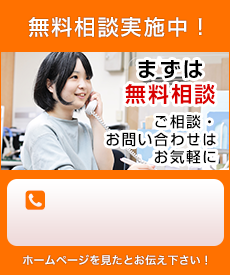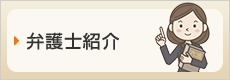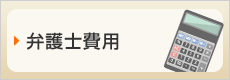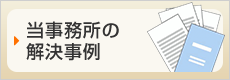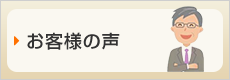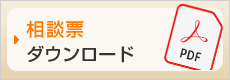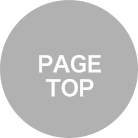不動産により遺留分が侵害された際の対応について弁護士が徹底解説!
目次
遺留分侵害額請求とは?
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合を指します。
民法では被相続人が遺言や生前贈与によってその財産を自由に処分する権利を認めていますが、まったく自由なわけではありません。相続人が不当に少ない財産しか受け取れない場合、その権利を保護するために遺留分が定められています。遺言や生前贈与があったとしても相続人には、最低限、受け取れる権利があります。
遺留分の対象となる財産とは?
遺留分は割合ですので、全体の財産のなかでその人がどのくらい遺留分として受け取れるのかを考えなければなりません。そのため、まず、遺留分の計算をするために、計算のもととなる全体の財産を明確にする必要があります。
遺留分の対象となるのは、
① 被相続人が死亡時に所有していた財産
② 相続開始前1年以内に行われた生前贈与が含まれます。
③ 法定相続人への生前贈与が特別受益となる場合には、原則相続開始前10年以内の贈与が対象となります(第三者の場合は原則1年以内)。
特別受益とは、簡単にいうと、複数の相続人がいるなかで、一部の相続人だけが生前贈与を含めて、亡くなった人の財産を受け取った利益のことです。相続人の間で、公平性を保つため、原則過去10年に遡って相続財産に持ち戻すことになっています。
遺留分の割合と計算方法
被相続人とどのような関係であるかによって遺留分の割合が異なります。
配偶者、子 遺産全体の1/2
直系尊属 遺産全体の1/3
兄弟姉妹 遺留分はなし(兄弟姉妹には遺留分が認められない)
例1
遺産総額6,000万円、遺言で配偶者のみに全部を遺贈した場合。
相続人として、配偶者、前妻との間の子2人がいる。
遺留分は6,000万円の1/2で3,000万円。
この金額をさらに配偶者と子供2人で分配
子供は2分の1で1500万円。子供は2人いるので、1人分はその半分の750万円
子供はそれぞれ配偶者に750万円を請求できる。
例2
遺産総額6,000万円、遺言で配偶者のみに全部を遺贈した場合。
相続人として、配偶者、被相続人の兄弟2人がいる。
被相続人の兄弟は、そもそも遺留分がないので、配偶者に遺留分を請求することが出来ない。
不動産によって遺留分が侵害されるケース
ほとんどの人は不動産を持っていると思います。不動産が遺産に含まれる場合、遺留分侵害が発生することがあります。その典型的なケースを以下に挙げます。不動産についての生前贈与や遺言があると、遺産分割や調停の場面でしばしば遺留分が問題になります。
生前贈与が偏っている場合
遺産の中に占める不動産の割合が大きい場合、預貯金があまりなく、不動産がほとんどの場合に、被相続人が特定の相続人に不動産を生前贈与すると、他の相続人はほとんど財産を取得できずに、遺留分侵害が発生する可能性があります。
事例
とくに地方では、先祖代々受け継いできた実家の土地建物をそのまま長男などへ継がせたいと考えることがあります。そのために、実家の土地建物を生前贈与することがあります。生前贈与をすれば遺産には含まれないので、相続のときに問題は起こらないと考えがちですが、実は、そのような場合には「持ち戻し」されてしまいます。不動産を生前贈与する場合に、その他の遺産として預貯金などがあれば、実家を継がない相続人も最低限の財産をもらえるのですが、実家の不動産がほとんどの場合だと、他の相続人の遺留分侵害がおこりやすいといえます。
遺言による不公平な分配
相続争いを避けるために、遺言書を作成し、遺言書で特定の相続人に不動産を集中させることがあります。この場合も、生前贈与の場合と同様に他の相続人の遺留分が侵害される可能性があります。遺言があれば、自由に財産を処分できるはず、後から文句は言われないはずと思い込んでいて、遺留分侵害のことを知らない人がいます。しかし、遺言があったとしても、遺留分の請求は法的に認められています。
事例
生前贈与の例でもあげたのですが、先祖代々受け継いできた実家の土地建物をそのまま長男などへ継がせたいと考えることがあります。そのために、実家の土地建物を遺言で遺贈することがあります。遺言を作るのはお勧めするのですが、遺留分侵害となることまで考えない人が多いのが残念です。遺言で不動産を渡す場合に、その他の遺産として預貯金などがあれば、実家を継がない相続人も最低限の財産をもらえるのですが、実家の不動産がほとんどの場合だと、他の相続人の遺留分侵害がおこりやすいといえます。よくあるケースです。
不動産による遺留分侵害の特徴・注意点
不動産による遺留分侵害には、他の財産にはない特徴と注意点があります。
不動産の評価基準の選択が必要
現金預貯金であれば、財産の評価は要りませんが、不動産の場合には財産をどのように評価するかが重要です。
不動産を評価する際には、以下の方法が一般的に用いられます。
① 固定資産税評価額:地方自治体が課税のために算定する評価額です。
②相続税評価額
路線価:相続税の評価基準で相続税の算定に使われます。
倍率評価:相続税の評価基準で路線価がない地域の土地について相続税の算定に使われます。
② 時価:市場での売却価格を基準とした評価です。変動しやすいため注意が必要です。
③ 不動産鑑定士の評価:不動産評価の専門家が行う公正な評価で、調停や審判の場で用いられます
不動産による遺留分侵害への対応方法
遺留分侵害が起こった場合にはどのように対応したらよいでしょうか。
話し合いによる解決
可能であれば相続人間での話し合いが最善です。話し合いがスムーズに進めば、調停や裁判を回避できます。
家庭裁判所の調停手続
相続人間で話し合いが難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停で話し合うという方法があります。調停は話し合いによる解決を目指す手続で、調停委員が解決を支援します。
訴訟提起
調停が不成立なら、地方裁判所に遺留分侵害請求訴訟を訴えて解決することができます。話し合いの手続ではなく、法律と証拠に従って法的な判断が下されます。
遺留分侵害を未然に防ぐ方法
まずは、生前贈与や遺言が遺留分侵害となるかどうかを事前にシュミレーションしておくことが必要です。そのためには、財産の調査を行う必要があります。
公平な遺言書の作成
推定相続人が誰であるか、その推定相続人の遺留分割合を調べましょう。
そして、財産のリストを作り、それぞれの評価額を記入し、全体財産と個別財産の評価額を算出しておきます。そのリストを特定の相続人に遺言であげた場合に、どのような数字の動きになるかを考えます。遺言書には遺留分を侵害しないよう配慮しましょう。
また、遺言書を作る場合には、可能であれば、事前に家族会議などで相続に関する考えや希望を伝えるようにしておきましょう。
生前贈与の管理
生前贈与も前記の公平な遺言書の作成と同じです。
推定相続人が誰であるか、その推定相続人の遺留分割合を調べましょう。
そして、財産のリストを作り、それぞれの評価額を記入し、全体財産と個別財産の評価額を算出しておきます。そのリストを特定の相続人に生前贈与であげた場合に、どのような数字の動きになるかを考えます。
生前贈与を行う場合、何をあげたのか贈与記録を管理し、相続人間の公平性を確保することが重要です。
不動産による遺留分侵害を弁護士に依頼するメリット
遺言書を作成する場合にも、遺留分侵害とならないかを相談しておくことをお勧めします。
また、逆に遺留分侵害請求をする場合には、その計算も、手続も複雑なので、弁護士に依頼することをお勧めします。特に、遺留分侵害額請求権は1年間で消滅してしまうので、早めに相談してください。
法的アドバイスの提供
一般の方が遺留分の仕組みをきちんと理解することは困難です。その点、専門家である弁護士は相続問題に精通しており、遺留分侵害に関する適切な法的助言を行うことができます。たぶん、本やネット読んで悩むよりも、簡単に遺留分のこと理解することが出来ます。
交渉代理
一般の方が遺留分の計算や手続を理解して自ら行うことは困難です。いたずらに苦労するよりは交渉を弁護士に依頼すると気持ちも楽になります。
手続きの代理
遺留分侵害額請求権に関することは、その多くが家庭裁判所への調停申立てや訴訟によって解決されます。必要な手続きを弁護士が代理人としてあなたに代わって行います。
不動産相続、遺留分侵害に関するお悩みは当事務所にご相談ください
不動産の相続問題は複雑で、遺留分侵害額請求もかなり詳しい法的な知識が求められます。当事務所では、遺留分侵害案件について、経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案いたします。相続問題でお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 相続登記義務化! 不動産の相続が発生する方へ
- 不動産相続をお考えの方へ。流れや要点を弁護士が解説!
- 不動産を特定の相続人に相続したい場合の注意点について弁護士が解説!
- 親と同居する子が実家の不動産を相続するためにやるべきことと注意点
- 不動産により遺留分が侵害された際の対応について弁護士が徹底解説!
- 賃貸物件を持つオーナーがすべき相続対策について弁護士が解説
- 離婚と相続が重なるときの法律問題-収益不動産・遺産の取り扱いを弁護士が解説
- マンションを相続する際の注意点と手続き、よくあるトラブルについて弁護士が解説
- ご自身の生活に不可欠な不動産を守りたい方へ
- 故人が所有していた収益不動産の相続をしたい方へ