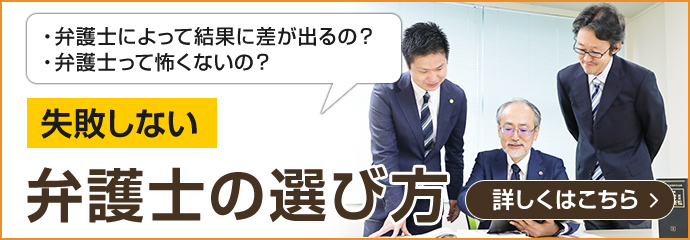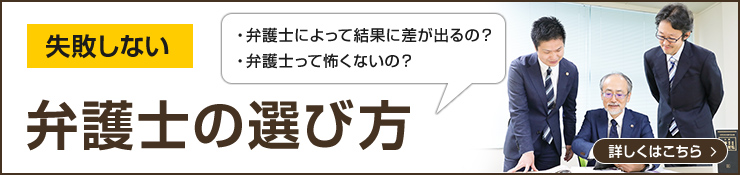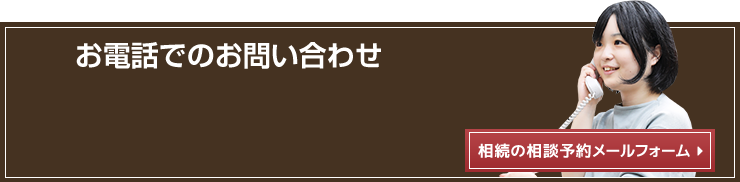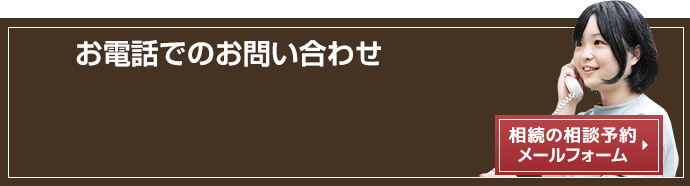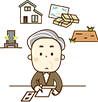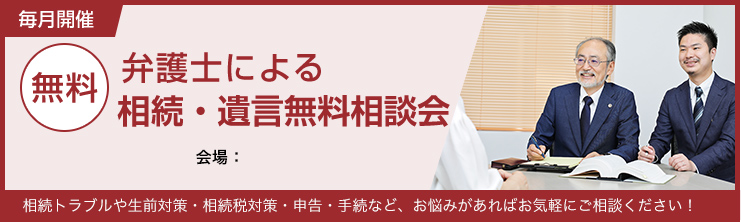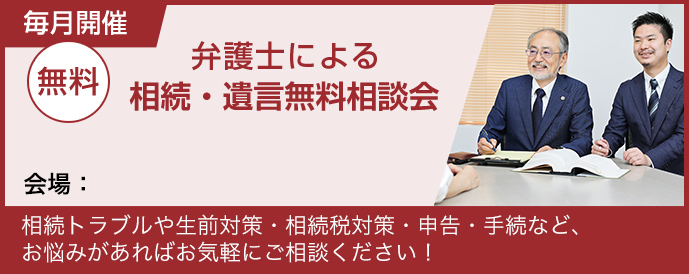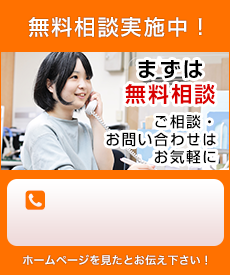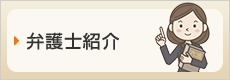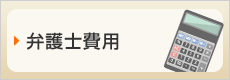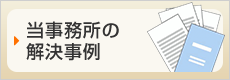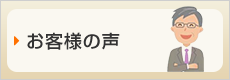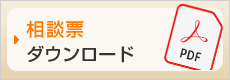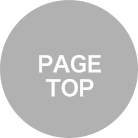相続の話し合いが長引くとき―遺産分割とお母様の生活を考え、終了した事例
- 2025.09.29
相談者情報
相談者
水戸市在住の男性(50代)
家族関係
被相続人:亡くなった父
相続人:母、兄、姉、相談者本人
相続財産
自宅、兄の自宅用地、神社周辺の土地、預貯金、生命保険金など
相談者のモノローグ(背景事情)
「父が亡くなり、相続の話し合いが始まりました。最初は土地や家屋の分け方からでしたが、話し合いを進めるうちに、母の生活費の管理や生命保険の受取人の問題まで広がってしまいました。兄は『お金の使い道を細かくチェックしたい』と言い、母の生活費まで管理しようとしています。母は『自分のお金は自分の判断で使いたい』と考えているので、その間で調整が難しく、どう進めるのがいいのか分からなくなってきました。兄の奥さんも積極的に意見を出してきて、話がどんどん細かく複雑になってしまっています。」
質問と弁護士の回答
質問1
「母の生活費を家族信託で管理したいという話が出ていますが、本当に必要でしょうか?」
弁護士の回答
「家族信託は、将来の認知症対策や大きな財産の管理には有効です。しかし今回のように、預貯金が限られていて日常の生活費中心という場合は、家族信託は過剰になりかねません。信託契約を結ぶと受託者や監督人の負担、費用も発生します。実務的には、合意書を作成し、定期的に通帳や領収書を確認・開示する仕組みをつくるだけで十分なケースも多いです。大切なのは、母の生活の自由を確保しつつ、他の相続人も安心できる仕組みを作ることです。」
質問2
「兄から『生命保険の受取人に自分の名前を入れてほしい』という要求があります。応じなければならないのでしょうか?」
弁護士の回答
「生命保険の受取人は、契約者と保険会社の契約によって決まります。相続人の一人が『自分を入れてほしい』と主張しても、契約者(今回はお母様)が同意しなければ変更はできません。代替案として、受取人に入っていない相続人へは、遺産分割で預貯金など他の財産を多めに配分して調整することが考えられます。保険金は“遺産”ではなく“受取人固有の財産”とされることが多いため、法律的には相続人全員で分け合うものではない点を理解しておく必要があります。」
質問3
「相続税を支払うために不動産を売却しました。その後の残っている土地や財産は、どう分けるのが適切でしょうか?」
弁護士の回答
「すでに売却して相続税の支払いに充てた財産は清算済みですが、残った土地・自宅・預貯金などは遺産分割協議の対象です。分け方としては、①母の居住を確保する、②公平性を意識して配分する、③将来の維持管理費用も考慮する、の3点が重要です。特に、自宅や神社の土地のように共有や管理が難しい財産については、売却か共有持分の調整を含めて具体的に決めておくべきです。遺産分割協議書をしっかり作成しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。」
弁護士からのアドバイスの要点
家族信託は万能ではなく、財産規模や目的に応じて検討すべき
生命保険金は遺産ではなく、受取人固有の財産となるケースが多い
合意書や協議書を通じて、「生活費の透明性」を確保する方法が有効
相続税の清算後の財産分割は、公平性と将来の管理を見据えて判断すべき
弁護士所感
この事例では、父の死後に相続財産をどう分けるかをめぐって、母の生活費の管理や生命保険の扱いまで議論が広がりました。相続の話し合いは一度始まると、財産の分け方だけでなく「生活の仕方」「お金の使い道」といった価値観の問題にまで及ぶことがあります。
教訓として大切なのは、感情的な主張を避け、ルールや合意書に基づいて調整すること相続税や不動産の管理など、将来にわたる負担も見据えて取り決めること。弁護士を交えて「常識的な基準」で線を引くことです。これにより、兄弟姉妹間の信頼関係を壊さずに円満解決へと導くことができます。
相続で悩んでいる方へ
相続問題は、財産の大きさにかかわらず「兄弟姉妹の気持ちのずれ」からこじれることが多いです。今回のように、母の生活費や生命保険の扱いなど、思いもよらない部分で衝突するケースは少なくありません。
みとみらい法律事務所(水戸市)では、相続に関する無料相談を承っています。遺産分割協議書の作成や、家族信託・遺言書のご相談にも対応可能です。一人で悩む前に、ぜひ一度ご相談ください。