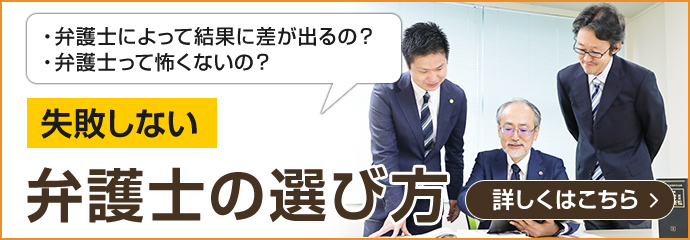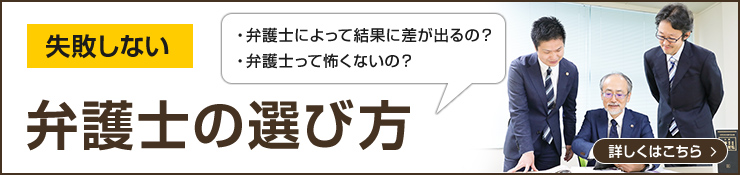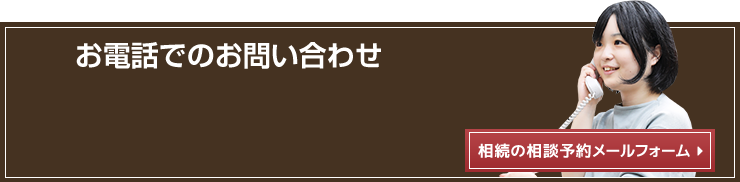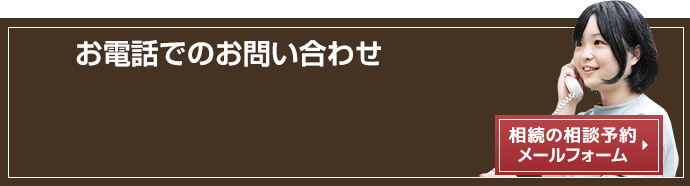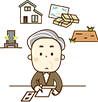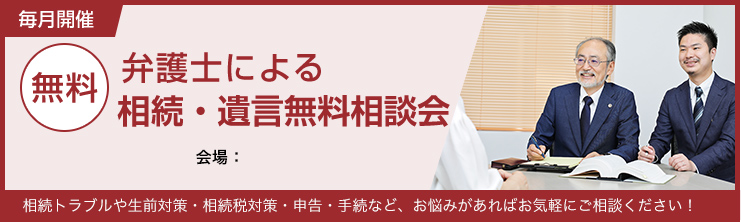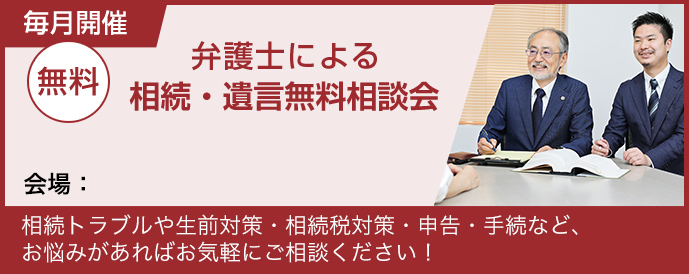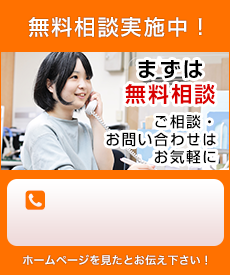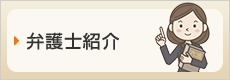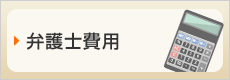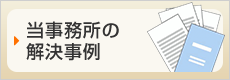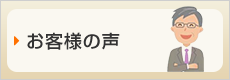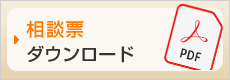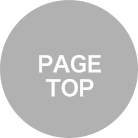【相談事例】相続から外された?—7年以上放置された遺産分割と遺留分請求の限界
- 2025.07.22
依頼者情報の整理
相談者
佐藤さん
年齢・性別
70歳(長女で4人きょうだいの長女)
被相続人
父(平成7年頃に死亡)
母(平成15年頃に死亡)
相続人
4人姉弟(相談者以外に3人)
相談者の背景事情
「私は4人姉弟の長女ですが、どういうわけか父母の相続の話から完全に外されてしまいました。7年も前に、他の3人だけで遺産分割を済ませてしまったようで、私には何の連絡も書類もありません。印鑑証明や実印も私は出していないので、本来であれば手続きできないはず。でも、不動産や預金の名義がどうなったのか、私には確認の術がなく、心情的にも納得がいかないままです…。」
質問と回答
質問①
「他の相続人が私の知らないところで勝手に遺産分割を済ませた可能性があります。確認する方法はありますか?」
回答
まず、相続人を勝手に除外して遺産分割協議をすることはできません。もし、心配であれば、お父さんは不動産を所有されていたとのことなので、その不動産の登記簿を法務局で確認してみてはいかがでしょうか。不動産の名義が誰か、もし、お父さんから名義が変更されていれば、いつ、誰に、どのような原因に基づき、変わったかを確認できます。また、相続当時の預金についても調べてみてはいかがでしょうか。金融機関に、除籍謄本とご自身の戸籍謄本を持参すれば、相続人としての資格を証明でき、残高証明書を取り寄せることが可能です(10年以内であればデータが残っている可能性が高い)。
質問②
「私の印鑑証明や実印が勝手に使われた可能性があります。それでも相続手続きは有効になりますか?」
回答
印鑑証明を、第三者が勝手に取得するのは困難です。そのため、ご自身が印鑑証明書を取得して渡したか、あるいは印鑑証明カードを渡していない限り、相手が印鑑証明書を取得することができません。また、実印もあなたが押印するか、実印を渡さない限り、相続手続の書類に押印されることはありません。そのような記憶がないかどうかもう一度思い出してみてください。もし、仮に印鑑が押された協議書が存在していた場合は、押印は「本人の意思に基づいてなされた」「遺産分割協議書は本人の意思に基づいて作成された」と推定されるため、覆すには明確な証拠が必要です。
質問③
「遺言があったらしいのですが、私には内容が開示されません。どう対応すればよいですか?」
回答
遺言書がある場合、その内容に従って相続が行われます。ただし、たとえ遺言があなたがもらえないような内容であったとしても、相続人には遺留分という最低限の取り分があります。とはいえ、遺留分侵害額請求権は「相続開始および遺留分の侵害を知ったときから1年以内」「相続開始から10年以内」が時効です。今回のケースでは、お母さんの死からすでに10年以上が経過しているため、遺留分請求は時効により困難と考えられます。
アドバイスの要点整理
• まずやるべき調査:法務局で登記簿確認、市役所で固定資産税の名寄帳取得、金融機関で預金状況確認。
• 印鑑証明がなければ勝手な手続きは不可能:偽造は一般的に考えにくい。印鑑証明やカードを渡したことがないか記憶を喚起してほしい。
• 生前贈与・遺言の可能性:もしかするとお母さんが生前に贈与を済ませていた、または他の相続人に有利な遺言を残していた可能性がある。
• 遺留分請求の時効:相続開始から10年を超えている場合、請求権は消滅する。
弁護士所感
今回の相談は、相続人間の不信感や感情のすれ違いが深く、そのため長期間にわたり放置されてしまったケースです。このような場合は、時間の経過により法的対応が極めて困難になります。相続問題は、「動くべきタイミングを逃さないこと」が非常に重要です。
遺留分請求には明確な時効があります。10年以上経過してしまうと、法的手段はほぼ閉ざされてしまいます。もし今回のように「自分だけ外された」「何も知らされなかった」と感じる場合には、できるだけ早く相続財産の状況を調査し、行動に移すことが大切です。
本件のような事情がある方は、お一人で抱え込まず、早期に専門家にご相談いただくことで、次の一歩を確実に踏み出すことができます。