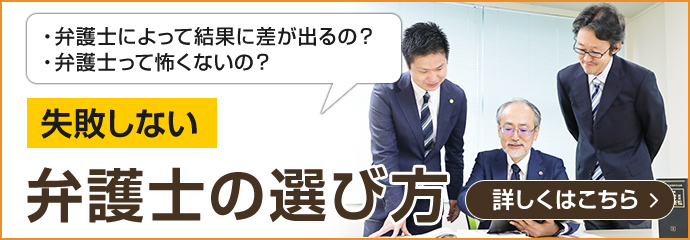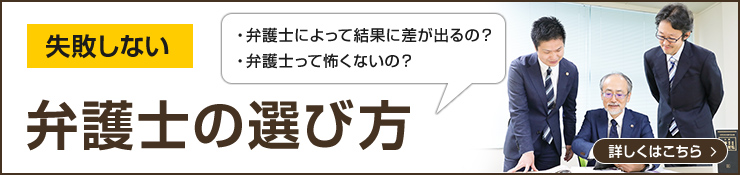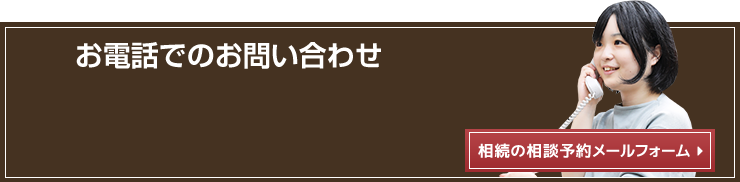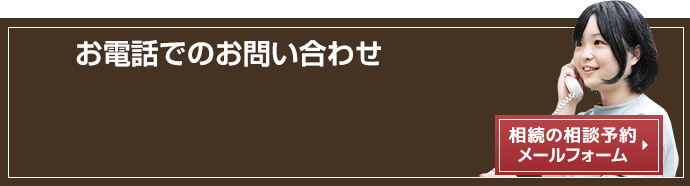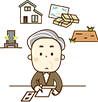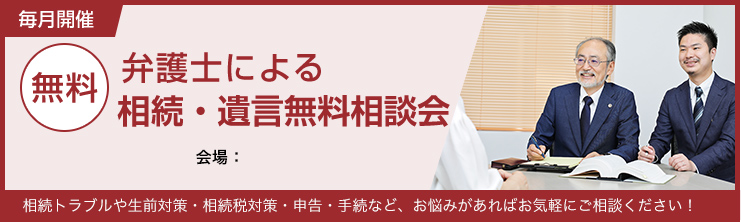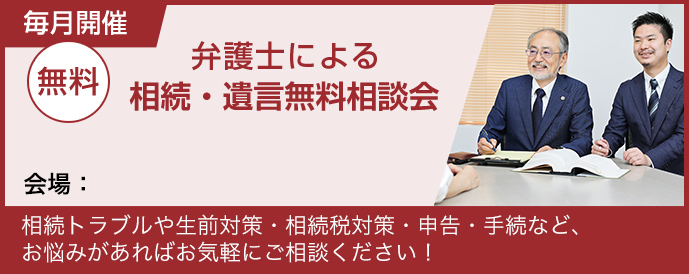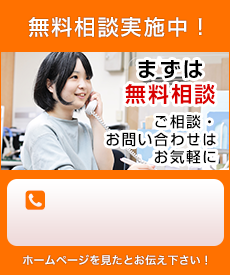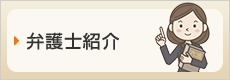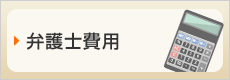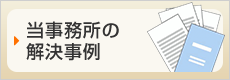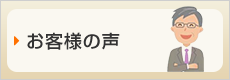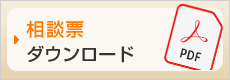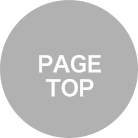祖母名義の土地が未相続のまま50年以上放置されていた事例
- 2025.07.22
依頼者情報の整理
相談者
斎藤さん(仮名)、65歳
住所
現在は茨城県外在住
家族構成
弟(独身・配偶者・子なし)、子供あり
被相続人
祖母(昭和45年に死亡)
本来の相続人
祖母の子(相談者にとっては父や叔父叔母)
現在の相続人
相談者・弟・代襲相続人を含む計26名(うち16名が面識なし)
相談者の背景事情
「私の祖母が亡くなってから、もう50年以上が経ちます。しかしその土地、つまり私の実家は、いまだに祖母名義のままで相続手続きがされていません。父が手続きしないまま亡くなり、私も弟も家を離れて久しく、家は空き家になっています。これまでも弟に手続きするよう促してきましたが、動いてくれず、私自身の相続のことも考えねばならない年齢になってきたため、今回ようやく動き出した次第です。司法書士に調べてもらったところ、まったく知らなかった親族が多数登場し、相続人が総勢26人という予想外の複雑さに直面しました…。」
質問と弁護士の回答
質問1:「知らない相続人が16人もいる場合、どのように相続手続きを進めればいいのですか?」
まずは、すべての相続人に対して通知・連絡を行い、遺産分割協議をお願いする必要があります。全員の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることになります。調停が不調に終わった場合は審判に移行し、裁判所が相続分に基づいて遺産分割方法を決定します。
質問2:「相続放棄や相続分放棄で、面倒な相続から逃れることはできますか?」
「相続放棄」は、家庭裁判所に申述することで最初から相続人でなかったことになりますが、被相続人の死亡後3か月以内が原則です。今回の場合は、すでに期間を経過しているため、相続放棄はできません。一方、「相続分の放棄」は、遺産分割協議の中で自己の取り分を放棄するもので、相続人で協議が成立すれば有効ですが、取り分をもらわないだけで相続人としての責任は残ります。
質問3:「全員の同意が得られない場合、どうすれば土地の名義変更や売却ができますか?」
全員の同意がない限り名義変更はできません。したがって、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申立てる必要があります。最終的には調停や審判によって裁判所の判断で分割・売却が行われることになります。
弁護士のアドバイス要点
- 遺産分割協議は全相続人の同意が必要
- 合意が得られない場合は家庭裁判所で調停・審判へ
- 相続人が多い場合は司法書士や弁護士による連絡・交渉が有効
- 相続分の放棄と相続放棄は手続きと効果が異なるため要注意
- 相続人が増え続ける前に、早急に手続きを開始すべき
弁護士所感(記事の結論)
今回のご相談のように、長年放置された未登記・未相続の不動産問題は、放置すればするほど相続人が増加し、手続きは複雑化します。また、相続人の多くが面識のない遠縁であるため、連携も取りにくくなります。
このようなケースでは、まず早期に専門家に依頼して相続人調査をしてもらい、それらの相続人と分割協議を進めることです。進展が見られない場合はすみやかに家庭裁判所に調停を申立てることが望まれます。
この事例から学べる教訓は、「相続登記の放置は、次世代への負担になる」ということです。相続は放置せずに早めの対応と専門家の関与が、将来的な負担を避ける鍵になります。