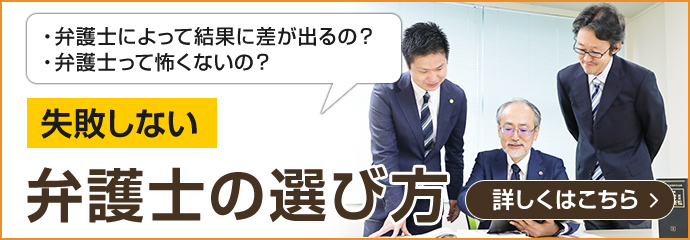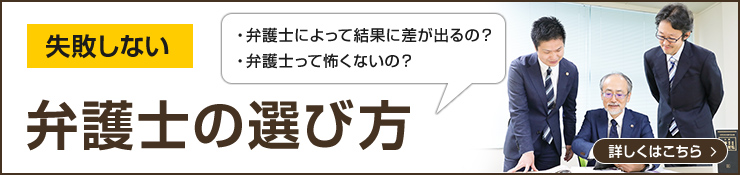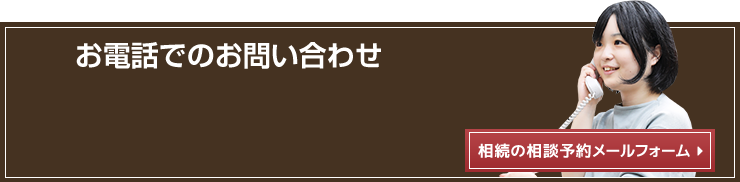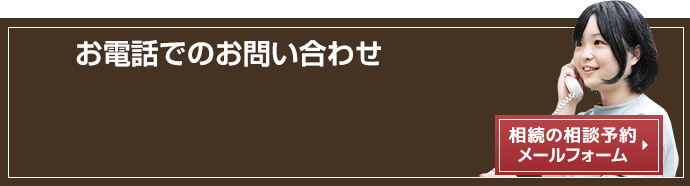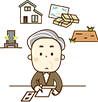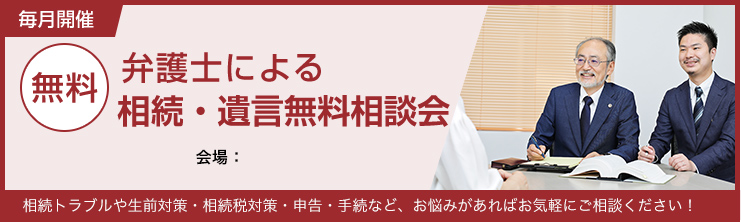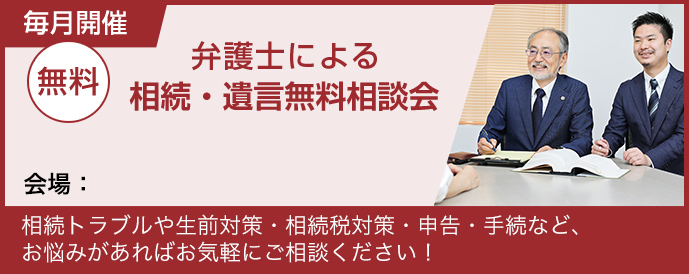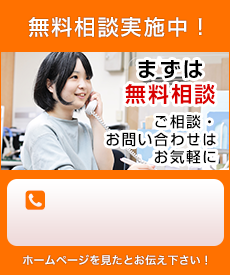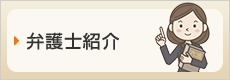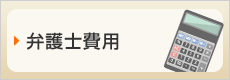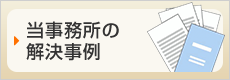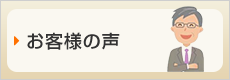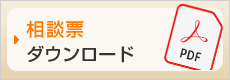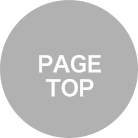【相談事例】特別受益としての住宅購入援助金をめぐる遺産分割トラブル
- 2025.07.22
依頼者情報の整理
氏名
Hさん(仮名)
年齢
60代
住所
ひたちなか市
被相続人
Hさんの父
相続人
Hさん(長男)、妹Aさん(次女)、弟Bさん(三男)
被相続人である父が亡くなり、相続が発生。遺言書は存在せず、兄妹3人で遺産分割協議を行うことになりました。しかし、父が生前に弟Bさんへ住宅購入資金として1,500万円を援助していたことが、今回のトラブルの発端となります。
相談者の背景事情
「父が亡くなって、相続の話を兄妹3人で進めることになりました。遺言書がないので、法定相続分に従って分ければよいと思っていたんですが、話が進まなくて…。というのも、弟のBが生前に父から住宅購入のために1,500万円もの援助を受けていたことが、今になって問題になっているんです。妹のAは『それは特別受益だ』と言い張り、Bの取り分を減らすべきだと主張していて…。正直、どうすればよいのかわかりません。」
質問と回答
質問1
「住宅購入資金の援助は、特別受益とみなされるのでしょうか?」
回答
住宅取得のための高額な生前贈与は、一般的に「生計の資本」としての援助とみなされ、民法903条に基づく「特別受益」に該当します。特別受益と認定されると、その援助分を一度相続財産に持ち戻して、全体の相続分を再計算する必要があります。
質問2
「援助を受けた弟が『親が好きで援助してくれたのだから返すつもりはない』と言っていますが、通りますか?」
回答
特別受益は、返還の義務があるという意味ではなく、公平な相続のために「贈与分を考慮して全体の取り分を調整する」という仕組みです。弟さんが援助を返す必要はありませんが、他の相続人と比べて相続分が多くなりすぎないよう、遺産分割にあたってその分を差し引かれる可能性があります。
質問3
「特別受益を考慮することで、遺産分割はスムーズに進みますか?」
回答
特別受益の金額やその評価時点に争いがある場合、むしろ協議がこじれることも少なくありません。そのため、証拠資料(贈与契約書、振込記録など)をもとに金額を確定し、相続人間の合意を形成していくことが重要です。合意が得られない場合は、家庭裁判所での調停や審判を通じて決着を図ることになります。
要点整理
• 住宅購入資金の贈与は、特別受益として遺産分割に影響を与える可能性が高い
• 特別受益の有無や金額については、証拠をもとに客観的に判断される
• 相続人間の公平を図るための制度であり、「返金義務」とは別問題である
• 話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも選択肢
弁護士所感(記事の結論)
この事例では、生前贈与が特別受益に該当するか否かが相続分に大きく影響しました。特別受益の判断は、金額の大きさや目的(生計の資本か否か)に大きく依存します。トラブルを防ぐためにも、生前贈与については記録を残し、可能であれば遺言書で明示しておくことが望ましいです。
相続人同士で感情的な対立が起きやすいテーマではありますが、法的な視点で冷静に状況を整理することで、公平な遺産分割が可能になります。早期に専門家へ相談することが、円滑な相続の第一歩です。