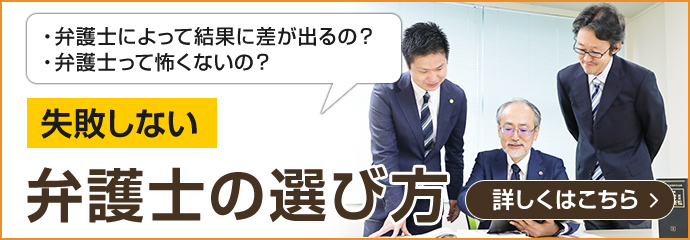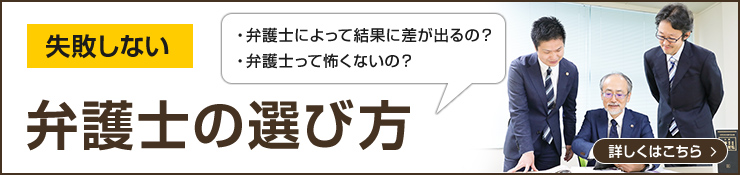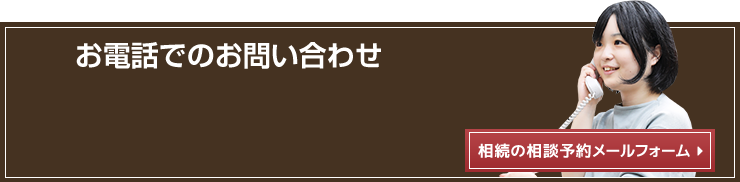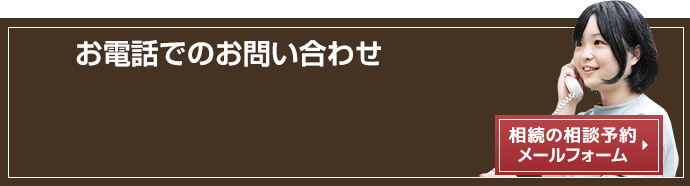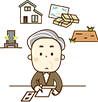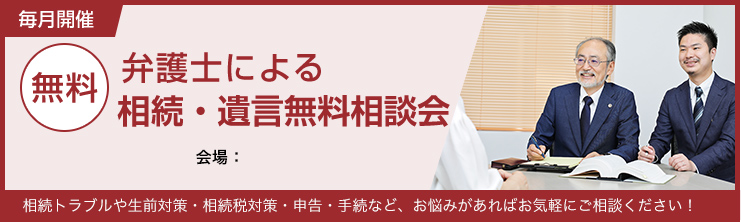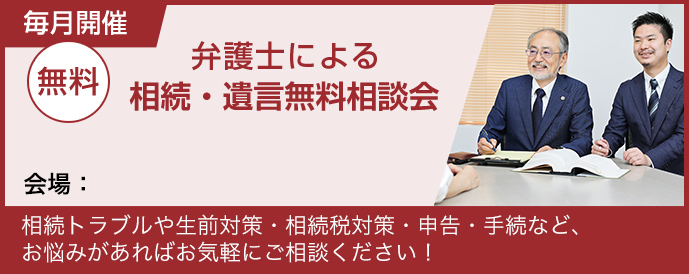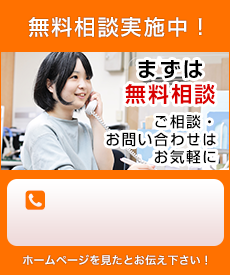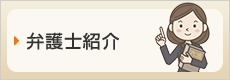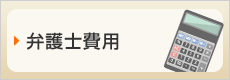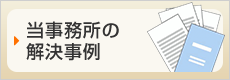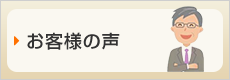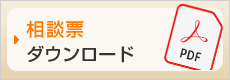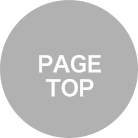「遠縁の相続、誰がどう負担するのか?」〜遺言のない叔父の遺産整理のサポート〜
- 2025.07.22
依頼者情報の整理
相談者
山本真由美さん(仮名・40代女性)
被相続人
叔父・山本弘一さん(仮名・千葉県在住・単身)
相続人
故人の兄弟姉妹とその子(合計10人、法定相続分に基づく)
背景
故人は未婚で子もなく、両親は既に他界しているため、法定相続人は兄弟姉妹およびその代襲相続人である甥姪が中心。相談者の山本さんは、実際の遺品整理・財産管理を一手に引き受けた立場で、他の相続人との公平な遺産分割方法について相談に来られました。
相談者の背景事情
「叔父が亡くなって、遺言書もなく、荷物や財産を整理するのは私になりました。もうホテル暮らしだった叔父の荷物を片付けたり、健康保険や年金の解約手続きをしたりと、かなり手間がかかりました。いくらか現金やテレホンカードなども出てきましたが、相続人は10人近くいて、しかもほとんど交流もなく…。みんな“任せるよ”という感じではあったけど、費用や労力の分担をどうすべきか、きちんと決めておきたくて相談しました。」
質問と回答
質問1
「相続人が多数いて連絡も疎遠です。どのように遺産分割を進めたら良いでしょうか?」
回答
まずは、全相続人を戸籍等で確定し、法定相続分を明示した上で協議を進める必要があります。実際に動いている相談者が遺産の一時取得者となり、他の相続人には後から金銭で分配する形式(代表取得)をとると、手続きがスムーズになります。持ち回りで遺産分割協議書に署名・押印を集める形式が一般的ですが、協議書を複数部作成して、個別に署名を集める方法(個別署名方式)を用いれば迅速に完了可能です。
質問2
「私が立て替えた費用や労力をどう反映すればよいですか?」
回答
相談者が立て替えた費用(葬儀費用、交通費、遺品整理等)は「相続人の共同の利益のための支出」として、遺産から差し引くことが可能です。また、実際にかけた時間や手間についても、他の相続人の了解があれば、相応の日当額を「労務対価」として加算することも認められます。明細やエクセル資料を基に具体的な数字を示すと、納得感が得られやすくなります。
質問3
「法定相続分ではなく、頭割り(等分)で分けたいのですが可能ですか?」
回答
可能です。遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば自由に内容を決定できます。法定相続分通りではなく、等分(頭割り)で分配する方法も取れます。その場合、提案内容を明文化した上で、全員の同意を得てから協議書を作成し、署名・押印と印鑑証明を集めてください。逆に、1人でも「法定相続分に従いたい」と主張すれば、そちらが優先される点に注意が必要です。
要点整理
• 相続人が多数いる場合でも、代表者が遺産を一括取得後に金銭で清算する方法が実務上有効。
• 立替経費や労力分は、具体的な費用・時間を明示することで、他の相続人の理解を得やすくなる。
• 分割方法(法定割合 or 頭割り)は、協議書案を2パターン用意し、相続人の合意形成を図ることが望ましい。
• 持ち回り署名方式は時間がかかるため、個別署名の協議書で一人ずつ署名を集める形式がおすすめ。
弁護士所感:多数相続人間の合意形成と費用負担の整理がカギ
今回のご相談は、遺言書のない相続と、多数の相続人による協議が必要な典型的なケースでした。特に、故人と疎遠だった相続人が多い場合には、実務を担う代表者(本件では山本さん)が大変な労力を強いられます。その分の実費・手間の補償をどう扱うかがトラブル防止の鍵となります。
事前に費用明細や日当計算をエクセルで提示し、協議書案を複数パターン用意する姿勢は非常に理にかなっています。相続トラブルを未然に防ぐためには、法的な正確さと、当事者間の納得感の両立が重要です。早い段階で専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進むことが期待できます。